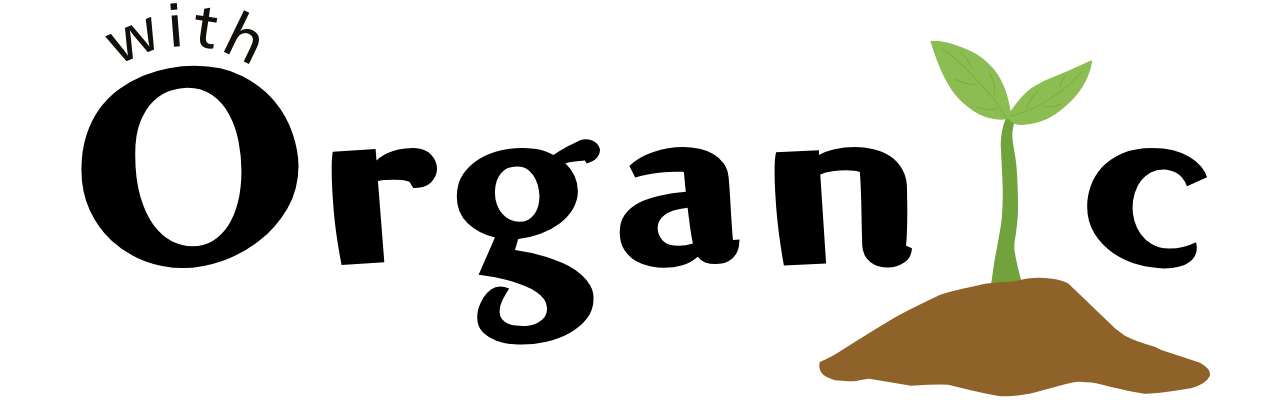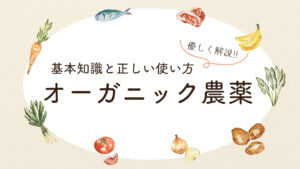街のスーパーやコンビニに行くと目に付くのは”有機栽培”や”特別栽培”と書かれた商品です。これらの言葉の違いにはどういった意味があるのでしょうか。それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

有機栽培とは
有機栽培とは、化学的な成分を含まない肥料や殺虫剤などの化学合成された農薬を使用せず、太陽・水・土地・生物など自然本来の持つ力を最大限に取り入れた栽培方法です。このような方法で栽培された農作物のことを「オーガニック」とも呼びます。
日本国内では、有機栽培された農作物には「有機JASマーク」という目印がつけられるため、そのマークで判別することが可能です。また、有機JAS認証制度には、下記のような規格が設けられています。
1.周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じている
2.は種又は植付け前2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しない
3.組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わない
引用元:農林水産省
無農薬栽培
無農薬とは、その農作物を栽培する過程において一切の農薬を使用していないことを保証したものです。
ただし、土壌に残留する化学肥料や他の畑からの混入した農薬の有無が曖昧であることから、現時点ではそういった厳格な基準や認定する機関がありません。そのため、消費者の誤認を防ぐために、農林水産省によって「無農薬」の表示は禁止されています。
減量農薬栽培
減農薬栽培とは、一般的な農業で使用される農薬に比べてその使用量を減らした栽培方法をいいます。また、農薬の中でも特に毒性の強いものはなるべく使用しないようにしています。このような方法で栽培された農産物を、最近では「特別栽培農産物」と呼ぶこともあります。
農薬が人体に与える影響とは
「オーガニック」という言葉を聞くことに慣れていく一方で、農薬の安全性や身体への影響に疑問を感じてしまうことも事実です。お次は、農薬の持つ役割や人体に与える影響についてご説明したいと思います。

日本の農薬って安全なの?
使用が許された農薬の規制はその国により異なります。
我が国日本では、除草剤、殺虫剤などといった農薬の安全性について、農林水産省をはじめとする各機関が連携を図りその農薬における毒性試験や安全性試験が行われ、ADI(一日摂取許容量)が定められています。
見た目も美味しそうであり、実際に食べても美味しいと感じるものを作るのは決して簡単なことではありません。特に、栽培過程で自然に大きく左右される農作物において農薬の使用をゼロでそれを実現することは極めて困難に近いのです。
一般的に日本国内で販売されている食材については、上記のように定められた基準をクリアしているものがほとんどですので、残留農薬の概念から見て安心と言ってよいでしょう。
しかし、欧米などでは通常使用されていない種類の農薬が、日本国内では現に使用されていることも事実なのです。

農薬の役割
農薬とは、害虫・病気・雑草など有害生物から農作物守るために使われる薬剤のことをいいます。
農薬取締法では、農作物の病害虫の防除に用いる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤及び農作物の生理機能の増進又は抑制に用いる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤を農薬と定義しています。農薬が身体へ与える影響
農薬が残った状態を残留農薬といいます。残留農薬の強い食材を摂取し続けることにより、身体的に様々な悪影響が現れるといわれています。
有名な症状の中には、 めまいや吐き気、皮膚のかぶれ、発熱、喉の渇きなどがみられるとされています。
また、風邪や持病などとは別で、このような身体的症状がある一定の期間改善されない場合やアレルギー症状が悪化するなどのケースでも、農薬中毒症状の可能性を疑うことがあります。また、残留農薬の影響はこうした身体面のみならず、精神面にも及ぶことも少なくありません。
こうした残留農薬の影響は、即時性が低くじわじわと時間をかけて身体へ悪い影響を及ぼす場合が多いとされています。
長期に渡る蓄積により数年後に健康被害が現れたり、アレルギー体質になりやすくなってしまったりすることがあるため、特に小さい子供がいる家庭などではなるべくオーガニックなものを取り入れたいと考える親も少なくないでしょう。
また、これから紫外線が特に気になるシーズンになれば、直接肌に触れるようなアイテムはより人体への影響が少ないものを選びたいですよね。
子供用の日焼け止めなども以下のような商品はとても安心感があり、使いやすいアイテムではないでしょうか。
残留農薬とは

残留農薬とは、農作物の栽培過程で作物に付着して収穫された野菜や果物に残っている農薬のことをいいます。また、残留基準は作物によりそれぞれ定められており、その基準を超えた物に関しては流通を制限されています。
残留農薬が残りやすい野菜
また、作物により残留しやすい作物と残りにくいものがあります。皮を剥いたりそのまま食べるようなものは比較的残留農薬が少ないとされている一方で、ほうれん草やケールなどの葉物や、いちご・りんごといったそのまま食べられるものは危険性が高いと言われています。
残留農薬が多いものランキング
【野菜編TOP5】
- ほうれん草
- ケール
- ピーマン
- トマト
- じゃがいも
【フルーツ編TOP3】
- イチゴ
- りんご
- ぶどう
- 桃
- さくらんぼ
残留農薬の落とし方
残留農薬の種類によっては、水洗いするだけでは落としきれないような成分も含まれています。そのような場合は、酢水や重曹水などを使用して落とすことができます。

【洗浄方法】
- 野菜・フルーツを流水でよく洗う。
- 酢と水を(1:3)で薄めた酢水、または食用重曹を一つまみ入れた重曹水を作る
- 皮の薄いものなら1分程度、皮が厚いものなら10分ほど(2)に浸す
- 流水で洗い流す
「有機栽培と無農薬栽培の違い」まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は「有機栽培と無農薬栽培の違い」についてまとめてみました。
”有機栽培”や”無農薬栽培”などのように、化学肥料や農薬を使用せず自然の力で作物を栽培するには、穣な土壌づくりが最も重要といえるでしょう。
また、健康的な作物が育つために土壌の生物活動を妨げないよう、有機物で栄養分を補い、自然由来の農薬や生物的防除法で病害虫を防ぐのがコツです。
便利な時代に生まれ育つ私たちやこれからの世代にとって「自然との共存」は決して容易いことではありません。しかし、少しの工夫や発想の転換により、安全で安心な野菜や果物を生み出すことができます。
自然由来の農薬や生物的防除法を活用することで、これからの地球環境を考え自然保護にやさしい持続可能な農業を実現しましょう。